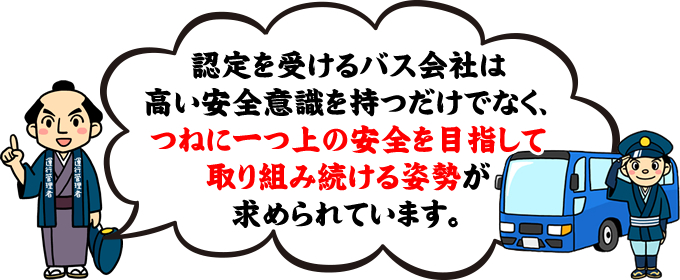「セーフティバス」マークはバス会社が安全対策にまじめに取り組んでいるひとつの指標になります。
「貸切バス事業者安全性評価認定」は、各バス会社から申請に基づき、任意で行うもので、法人単位での認定評価となります。申請は、日本バス協会の会員以外でも可能です。評価制度の実施と運営は日本バス協会と、学識経験者や有識者、国土交通省、日本バス協会の認定委員8名で組織する「安全性評価認定委員会」が行っています。
認定を希望するバス会社は、以下8つの項目における条件をすべて満たしていることが条件になっています。
評価認定はまず、日本バス協会において 1.安全性に対する取り組み状況、2.事故及び行政処分の状況、3.運輸安全マネジメントの取り組み状況について書面と訪問審査を行います。
書類審査は法令順守事項ももちろん含まれています。
たとえば、記録機能をもつ、アルコールチェッカーを使用し、厳正な点呼を行っているか、デジタルタコグラフやドライブレコーダーを導入しているか、法令順守事項よりも高いレベルで安全対策に取り組んでいるかなどを審査していきます。
3つの取り組み状況の評価点数合計が合計60点以上であること。各評価項目が基準点以上であることが条件。ただし、合計点数が60点以上でも、一つの項目が基準点を下回る項目がある場合は認定されません。
この後、各バス会社の1営業所を訪問し、日々の業務が適正に行われているかが審査されます。
すべての条件を満たしている場合であっても新規申請の場合はすべて「一ツ星」認定からスタート。認定有効期間は2年間で、その間に事故を起こす、行政処分を受けるなどがあれば認定取り消しになります。
認定取り消しとなった事業者は、取り消し日から約1週間、日本バス協会のホームページで公表されます。
詳しくは日本バス協会が提供しているセーフティバスの紹介パンフレットを参考にしてくださいね。